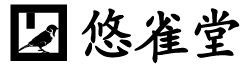前回の「健康サービスを考える(その3):生体センサのまとめ、提案、そして余談」にて、生活者向けの腕時計型ライフレコーダーを提案しました。
本稿ではそれに関してさらに考察をすすめ、腕時計の裏蓋型センサを提案します。そして測定する生体情報の項目についてのコンセプトを考えてみます。
センサ形状の再考察
前稿では、「弱い締め付けが受け入れられるのは手首くらいだろう」として、ありきたりですが腕時計型を提案しました。
(他にも弱い締め付けが許容されているということで、くるぶしの後ろ辺りに靴下で圧迫する形状も考えました。しかしアルゴリズムの作りなおしが必要ですし、素足やストッキングの場合は付けてもらえません。)
もう少し形状について考察してみます。
課題-ファッション性
腕時計やリストバンドの重要な機能として、ファッション性が挙げられます。
前稿に挙げた商品投入各社もデザインは重要視しており、様々な色が用意されていたり、ホームページには有名?デザイナがデザインした、というような記載があったりします。
しかし、ある種の画一感は否めません。
また腕時計をするに人にとっては、「腕時計と同じ腕に付けるか?反対の腕に付けるか?」という問題があります。腕時計と同じ腕につけるとちょっとかっこ悪いですし、反対の腕(おそらく利き手)に付けるのは慣れるまで大変そうです。
提案-腕時計の裏蓋型
そこで提案なのですが、腕時計の裏に貼り付けるような形状はどうでしょうか?
時計のバンド調節を、裏に3mmくらいの厚さの物が入っても良いくらい緩めにして、時計の裏に貼り付けたセンサがちょうど体に密着するようにします。エアーやスポンジのクッションが必要かもしれません。
時計を変えた時も、センサを張り替えればOKです。「センサのためにバンドを調整し直すのは面倒」という人には、センサの純正オプションとして時計を売ることも考えられます。
難を言えば、センサが女性用時計より小さくならない、そもそも緩めの時計が好きな人には合わない、ということが考えられます。ある程度フィットした兼用の時計にしてもらう必要はありそうです。(それでも現状の画一感より選択肢は広がります。)
上のようなコンセプトから、目標とするセンサの形状は直径30mm以下、厚さ3mm以下ということになります。
果たしてこのサイズに必要なチップとバッテリーが実装できるでしょうか?
測定項目のコンセプト
測定項目のコンセプトとしては、以下の3点を考えました。
- 馴染みの測定項目
- 健康状態のアドバイス
- 実感
本章では、測定コンセプトのそれぞれについて書きたいと思います。
馴染みの測定項目
まず「馴染みの測定項目」とは、普通の人が、数値から何となく自分の状態が意識できる測定項目のことです。具体的には以下が挙げられます。
体重
身長との関係から理想体重とかBMIとかもありますが、それより何より、人それぞれ自分の「ベストな体重」がイメージできるのではないでしょうか。
またダイエットしている人、筋肉量を増やそうとしている人などはそれぞれ目標の体重を設定し、それを目指しているのだと思います。
活動量
測り始めると、その日の自分の行動との関連付けが容易でイメージしやすい測定項目です。私は「カロリー」表示の活動量計を試したことはありませんが、携帯の万歩計機能を試してみた時は「普通は一日8000歩。一日一万歩以上歩くと運動した気になる」という感覚を持ちました。
体温
家庭に体温計があり、「熱っぽい」ときに測ってみたりします。またある閾値で「発熱」と判断されます。
子供の頃の記憶から、その閾値は「37.0度」と思っていたのですが、Wikipediaによると「臨床的に発熱とは37.5°C以上のものを指す」とのことです。(微熱、中程度の発熱、高熱の区別もありました。)子供・大人によっても基準が違うのかもしれませんね。
血圧
中年になると自然に血圧が上がってきて、健康診断の際に「注意してくださいね」といわれます。気にするようになると「上が140、下が90」という閾値を覚えます。
測定項目の利用法
これらの「馴染みの測定項目」は、単なる数値表示や日々のグラフでも、ユーザーが意味を見出して解釈してくれます。また体温や血圧などは客観的な基準値も明確なので、それと比較して表示に反映させる(例えば数値表示を黄や赤にする)ことも可能です。
健康状態のアドバイス
次に「健康状態のアドバイス」についてです。これに含まれる測定項目は、その値によってアプリケーションがアドバイスを提示することが可能です。
測定項目
これに含まれる測定項目としては、「親しみやすい測定項目」にも挙げた、体温と血圧があります。
- 体温 : 感染や炎症の指標となります。値を見てすぐに受診したり解熱剤を飲んだりすることができる、短期的な指標です。
- 血圧 : 高血圧は、心血管病、腎臓病のリスクになります。しかし上の血圧が140位上になると即病気、ではありませんし、突然高血圧になる、という状況も多くないと思います。長期的にモニタすべき指標と言えます。
「ウェアラブルなセンサ」という観点から考えると、正確に上の項目が計測できる必要はありません。体温(深部温か腋窩温)と相関のある推計値、あるいは血圧と相関のある推計値が計測できればOKです。
またメタボリックシンドロームの診断基準である腹囲のような、内臓脂肪の量と相関がある値も計測できたらよいですね。
推計値の利用
推計値によって「今朝は熱っぽいようです。体温を測ってみませんか?」とか、「最近血圧が高いような気がします。測ってみませんか?」のようにアプリが提案することができます。それを見たユーザーはちゃんとした医療機器で計測し、その計測値をもって受診や生活改善をするなどのアクションを取るようにします。(節のタイトルには「健康状態のアドバイス」と書きましたが、正確には「健康状態を正確に確認することへのアドバイス」です。)
面倒ですが、正確な値をアプリに入力するようにすれば、推計値の校正にもなりますし、アドバイスのコンテンツにも誘導できます。(医療機器と連動のアプリが誘導するのかもしれませんが。)
馴染みの測定項目への転換
体温、血圧、体脂肪とも、健康なときはさほど気にしません。
アプリによって「健康状態のアドバイス」がなされた後、気にするようになって始めて定期的に確認したくなります。定期的に確認することで「馴染みの測定項目」に転換されます。
そして体温のように、健康に戻るとまた確認しなくなります。
実感
最後に「実感」ですが、これが一番難しく、またブレストしがいのあるコンセプトだと思います。
「実感」とは
ダイエットや体づくりなど理想の健康状態を目指している人、レコーディングマニアな人を除く普通の人にとっては、「馴染みの測定項目への転換」が起こらない限り「測定項目を見たい」というニーズは起こりにくいと考えます。
最初は物珍しさで装着してもらえるかもしれません。しかしずっと健康状態で「健康状態のアドバイス」がなされない場合、センサ自体を装着するモチベーションが下がり、使ってもらえなくなるでしょう。(ぶら下がり健康器状態。)
そこで何か、センサを装着することを動機づけるための工夫が必要になります。
それは「楽しい実感」かも知れませんし、「健康の実感」かも知れません。「実感」という言葉自体も適当ではないかもしれません。それこそコンセプト創造が必要です。
センサを装着することを動機づけるもの、ユーザーが有意義さを感じるもの、そしてユーザーがアクションを取った時にフィードバックがなされるようなしくみを、とりあえず「実感」ということにします。
既存の実感
あやふやな概念ですが、既にサービスに組み込まれている「実感」を挙げます。
SNS
クラウド型サービスの中にSNSがあったり、Twitterやfacebookなどの既存のSNSと連携したりします。
私はユーザーではないのでわかりませんが、ダイエットなどではお互い励まし合ったりするのでしょう。
だいぶ前にtwitterで、フォローしている人の体重tweet(±値だったかもしれません)を見たことがあります。公開することで強制力がでるのでしょうか。(そのうち見なくなりました。。。)
ゲーミフィケーション
ゲーミフィケーションとしては以下があります。
- 可視化・イベント : 昔あった、東海道万歩計やヤマト万歩計です。累積歩数を日本橋からの宿や、地球からイスカンダルまでの距離に換算しなおして表示するとともに、一定量でイベントが表示されます。(波動砲発射など)
- ポイント・バッジ : 歩数などをポイントに換算しユーザーにキックバックします。そこまで行かなくてもバッジ(単なるアプリのデータ)が表示されたりします。
- 競争 : SNSとの連携ですが、ある期間で一番歩いた人が表彰されます。
文字通り、ゲームの要素にしてしまうことも可能です。たまごっちやポストペット的なものは作れそうですね。(私は両方共やったことはないので、結構テキトーなことを書いています。爆)
以上は万歩計の機能ですが、その他の測定項目でも何か考えられるでしょうか。
課題
既存の「実感」を挙げてみましたが、どうも既に「馴染みの測定項目」について更にモチベートする仕組みのようです。
「健康状態のアドバイス」が提示される前のサイレントな状態で、「実感」に繋がるアイデアが必要そうですね。
まとめ
前稿で提案しましたセンサの表を、今回のコンセプトと照らし合わせ修正しました。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形状 | 時計の裏に装着できる形状 (直径30mm、厚さ3mmくらい) |
| オプション | センサを装着・表示できる時計 |
| センサ | 測定コンセプトと項目 |
| 加速度 | 「馴染みの測定項目」 活動量(歩数、カロリー、活動状態) |
| 脈波 | 心拍数 「健康状態のアドバイス:長期的」 血管の固さの指標 簡単な不整脈検出 「実感」 交感神経・副交感神経バランス(心拍変動より) |
| 心電+脈波 | 「健康状態のアドバイス:長期的」 血圧の推計値 (脈波伝搬時間より) |
| ?(あったらいいな) | 「健康状態のアドバイス:短期的」 深部体温の推計値。(撓骨動脈の平衡温) |
(心拍数が浮いていますね。スポーツ向けでない限り、「心拍数を表示してどうなの?」って感じです。)
「実感」のコンセプトに適合する測定項目として、交感神経・副交感神経バランスを挙げました。しかし任天堂さんがwiiバイタリティーセンサーをペンディングにしたように、心拍変動の実用化にはまだまだ越えなければならない山があるように思います。
次回はこの心拍変動について書きたいと思います。